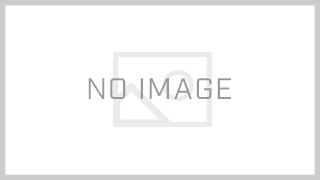パーマ剤の組成(過去出題)
パーマ剤は、還元剤を有効成分とする第1剤と、酸化剤を有効成分とする第2剤で構成されています。
第1剤にはその作用を増強させる目的で、アルカリ剤が追加されることが多いです。
パーマ剤第1剤の有効成分→還元剤
パーマ剤第2剤の有効成分→酸化剤
第1剤の作用を増強させるもの→アルカリ剤
パーマの原理
第1剤の作用原理
第1剤を毛髪に作用させると、以下のような順序で作用が起こります。
- 水で水素結合が切断される。
- 毛髪は膨澗、軟化し、イオン結合もアルカリで切断される。
- 毛髪はさらに膨潤、軟化する。
- 膨澗、軟化した毛髪内に浸透した還元剤(チオグリコール酸・システインなど)のはたらきにより、毛髪内のシスチン結合(ジスルフィド結合)を還元し、切断する。
- ロッドに巻かれた毛髪はケラチンの架橋構造にずれを生じた状態となっている。
第2剤の作用原理
第1剤塗布後ケラチンの架橋構造にずれの生じた状態で第2剤を作用させると、以下のような順序で作用が起こります。
- 酸化剤(臭素酸ナトリウム・臭素酸カリウム・過酸化水素水など)のはたらきにより、ずれを生じたままシスチン結合が酸化され、再結合する。
- この状態で毛髪は安定し、ウエーブが形成される。
共有結合(=シスチン結合)(=ジスルフィド(s-s)結合)
- 硫黄同士の結合
- 結合力→とても強い
- 還元剤で切断される
イオン結合
- イオン同士の結合
- アルカリで切断される
水素結合
- 水同士の結合
- 結合力→とても弱い
- 水で切断される
パーマ剤の分類
パーマ剤は、医薬部外品に分類されます。(医薬品医療機器等法により)
パーマ剤は、以下のような種類があります。↓
| 二浴式 | 第1剤と第2剤からなるパーマ剤のこと。 |
|---|---|
| 一浴式 | 二剤を使わず、空気中の酸素による酸化を用いるパーマ剤。 |
| コールド式 | 室温で用いるパーマ剤。 |
| 加温式 | 遠赤外線促進機などで60℃以下に加温して用いるパーマ剤。 |
医薬部外品には何がある?↓

パーマ剤第1剤の組成(過去出題)
パーマ剤第1剤の構成は、以下の通りです。
- 有効成分(還元剤)
- 作用の増強(アルカリ剤)
- 水
- 添加剤(界面活性剤、金属イオン封鎖剤、油性成分、ポリペプチド、香料など)
パーマ剤第1剤 = 還元剤 + アルカリ剤 + 水 + 添加剤
①有効成分
パーマ剤第1剤の有効成分は、還元剤です。
還元剤は、チオグリコール酸、システイン、チオグリコール酸アンモニウム、などです。
作用の増強
パーマ剤第1剤の作用の増強には、アルカリ剤が使用されます。
アルカリ剤は、アンモニウム水、炭酸水素アンモニウム、エタノールアミンなどがあります。
第1剤の有効成分は基本的にアルカリ性の物質からなります。作用の増強も、アルカリ性のものを混ぜて強アルカリにすると覚えましょう。
溶剤
溶剤には、水が使用されます。
添加剤
界面活性剤、金属イオン封鎖剤、油性成分、ポリペプチド、香料など
特徴
- 毛髪のケラチンの化学構造の一部を還元し、切断する。
次の有機酸のうち、パーマネントウェーブ用剤第1剤の有効成分である還元剤はどれか。
(1) 酢酸 (2) クエン酸 (3) チオグリコール酸 (4) グリコール酸
パーマ剤第1剤に含まれる還元剤は、次のうちどれか
(1) シスチン (2) チオグリコール酸 (3) 臭素酸ナトリウム (4)過酸化水素
パーマ剤第2剤の組成(過去出題)
パーマ剤第2剤の構成は、以下の通りです。
- 有効成分(酸化剤)
- 水
- 添加剤(界面活性剤、金属イオン封鎖剤、pH調整剤、油性成分、ポリペプチド、香料など)
パーマ剤第2剤 = 酸化剤 + 水 + 添加剤
有効成分
パーマ剤第1剤の有効成分は、酸化剤です。
酸化剤には、臭素酸ナトリウム、過酸化水素水、臭素酸カリウム、過ホウ酸ナトリウムなどが使用されます。
第2剤の有効成分も基本的に酸性の物質からなります。
溶剤
溶剤には、水が使用されます。
添加剤
界面活性剤、金属イオン封鎖剤、pH調整剤、油性成分、ポリペプチド、香料など
第2剤の特徴
- 切断されたシスチン結合を再結合する。
臭素酸ナトリウム→過酸化水素水と比べて酸化力がおだやか。
- その分、十分な作用時間を必要とする。
- 酸化による過剰作用が起こりにくいため、毛髪を損傷するおそれが少ない。
過酸化水素水→臭素酸ナトリウムと比べて酸化力が強い。
- 作用時間は短い。
- 第1剤のアルカリ剤が毛髪に存在すると、アルカリ剤を過酸化水素水が分解し、毛髪を脱色するおそれがある。
- 作用時間が長過ぎると酸化による過剰作用で毛髪を損傷するおそれがある。
酸化力の強さ 過酸化水素水>臭素酸ナトリウム
パーマ剤の有効成分に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「二浴式のパーマ剤は、( A )のような( B )を有効成分とする第1剤と、( C )のような( D )を有効成分とする第2剤からなる。」
(1)A:臭素酸ナトリウム B:還元剤 C:チオグリコール酸 D:酸化剤
(2)A:臭素酸ナトリウム B:酸化剤 C:チオグリコール酸 D:還元剤
(3)A:チオグリコール酸 B:還元剤 C:臭素酸ナトリウム D:酸化剤
(4)A:チオグリコール酸 B:酸化剤 C:臭素酸ナトリウム D:還元剤
正解(3)
パーマ剤の使用上の注意
パーマ剤は、強力な薬剤なので、取扱いや使用方法を守らないと毛髪や皮膚を傷めたり、効能・効果にも悪影響があるので注意が必要です。
パーマ剤で、まつ毛への使用が認められた製品は存在せず、まつ毛のパーマは禁止されている。
【参考】まつ毛パーマって禁止なの?(mememag様)
https://www.mememag.me/hairbeauty/qa/6645/
パーマの一連の流れ
| 施術工程 | 注意点 |
| 毛髪診断 | (施術を避ける場合)
|
| シャンプー |
|
| ロッド巻き |
|
| 第1剤塗布 |
|
| 中間水洗 |
|
| (アイロン操作) |
|
| 第2剤塗布 |
|
| 水洗 |
|
パーマ剤まとめ
【1剤(還元剤・アルカリ性)】
還元剤→チオグリコール酸・システインなど
水素結合・イオン結合・シスチン結合を切断。
【2剤(酸化剤・酸性)】
酸化剤→臭素酸ナトリウム・臭素酸カリウム・過酸化水素水など
酸化力の強さ 過酸化水素水>臭素酸ナトリウム
ずれを生じたままシスチン結合を酸化、再結合。
パーマ剤まとめ問題
酸化剤と還元剤に関する次の記述のうち誤っているものはどれか
(1) ヘアブリーチに利用されている酸化剤は、主に5〜6%の過酸化水素水である。
(2) パーマ剤の第1剤は,毛髪のケラチンの化学構造の一部を還元して切断する。
(3) パーマ剤の第1剤の有効成分は,臭素酸ナトリウムであり,第2剤の有効成分は、チオグリコール酸である。
(4) パーマ剤の第2剤は、毛髪の切断されたシスチン結合を再結合する。
正解(3)・・・パーマ剤の第1剤の有効成分は,チオグリコール酸であり,第2剤の有効成分は、臭素酸ナトリウムである。
パーマ剤に関する次の記述のうち, 正しいものの組合せはどれか。
a ケラチンのシスチン結合は,酸化剤を作用させると切断できる。
b 一浴式パーマ剤には,二浴式パーマ剤第1剤の有効成分と第2剤の有効成分の両方が含まれている
c 二浴式パーマ剤第1剤の有効成分のうち、システインはチオグリコール酸よりウェーブ形成力が弱い
d 二浴式パーマ剤第2剤の有効成分のうち、過酸化水素水は臭素酸ナトリウムに比べて酸化力が強い。
(1) aとb (2) bとc (3) cとd (4) aとd
正解(3)
a・・・ケラチンのシスチン結合は,還元剤を作用させると切断できる。
b・・・一浴式パーマ剤には,二浴式パーマ剤第1剤の有効成分と第2剤の有効成分の両方が含まれているわけではない。
パーマネント・ウェーブの原理に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「カーリングロッドに毛髪を巻いて第1剤を作用させると、毛髪を形成するクラチンの 架橋構造(側鎖)の( A )結合がチオグリコール酸などの ( B )により切断され、次に第2剤を作用させると、含まれる( C )などの薬剤の働きにより架橋構造にずれを生じた状態で( A )結合が復元し、ウェーブが固定される。」
(1) A:ペプチド B:還元剤 C:アンモニア
(2) A:ペプチド B:酸化剤 C:臭素酸ナトリウム
(3) A:シスチン B:還元剤 C:臭素酸ナトリウム
(4) A:シスチン B:酸化剤 C:アンモニア
正解(3)
パーマ剤に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1) 第2剤に用いられる酸化剤には,システイン,システインの塩類が用いられる。
(2) 第1剤には,還元剤として,チオグリコール酸,またはその塩類が用いられる。
(3) 第1剤には、還元剤の他浸透剤や乳化剤が用いられる。
(4) 第1剤に配合されるアルカリ剤は, アンモニア水, エタノールアミンなどが用いられる。
正解(1)・・・第1剤に用いられる酸化剤には,システイン,システインの塩類が用いられる。
パーマ剤に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1) 同一濃度,同一pHの場合,チオグリコール酸よりシステインの方がウエーブ形成力は強い。
(2) 同一成分で同一pHでは,成分の多い方がウエーブ形成力は強い。
(3) システインは酸化されると毛髪のケラチンに含まれるシスチンになるため,損傷をうけた毛に適した運元剤である。
(4) pHが高いほと膨潤度が大きくなり, ウエーブ形成力が強い。
正解(1)・・・同一濃度,同一pHの場合,システインよりチオグリコール酸の方がウエーブ形成力は強い。
パーマの基本的な施術行程と特に注意する文章のうち正しいものはどれか
(1) 前回のパーマ施術及び染毛(酸性染毛剤を除く)してから1ヶ月以内の場合は施術を避ける。
(2) コールド式の薬剤をヘアアイロンで加熱するときは180℃以上にする
(3) 眉毛やまつ毛に施術する事は禁止されている。
(4) 第2剤の臭素酸塩と過酸化水素水を混合するとパーマがかかりにくい毛に有効である。
正解(3)
(1) 前回のパーマ施術及び染毛(酸性染毛剤を除く)してから1週間以内の場合は施術を避ける。
(2) コールド式の薬剤をヘアアイロンで加熱するときは180℃以下にする
(4) 第2剤の臭素酸塩と過酸化水素水を混合することはしない。
パーマの基本的な施術行程と特に注意する文章のうち、正しいものはどれか、
(1) コールド式のものは,温度60℃以下を守る。
(2) 2浴式には第1と第2剤があり,使用直前に混和する
(3) 眉毛およびまつ毛への使用は禁止されている。
(4) 水洗は薬剤を洗い流す目的で,最後にだけ行う。
正解(3)
(1) 加温式のものは,温度60℃以下を守る。
(2) 2浴式には第1と第2剤があるが,これらを混和することはない。
(4) 水洗は薬剤を洗い流す目的で,中間水洗と最後に行う。
パーマ剤第1剤に加えられるアルカリについての次の記述のうち正しいものはどれか。
(1) 第1剤の作用時間中に揮発し過剰作用のおそれがなく,水で簡単に洗い落とせるため,手荒れの心配が少ないのは炭酸水素アンモニウムである。
(2) 強いパーマ剤は得られないが,臭気が弱く作用も弱いため毛髪や皮膚に対しても悪影響をあたえず,手荒れの心配の少ないものはモノエタノールアミンである
(3) 臭気がない反面,揮発しにくく皮膚への親和性が高いので,過作用のおそれがあり,水で洗い落としにくく手荒れに注意する必要があるのはアンモニア水である。
(4) パーマには, 主に有機アルカリの方が毛髪の膨潤度が大きく作用する。
正解(3)・・・有機アルカリ=モノエタノールアミン
(1) 第1剤の作用時間中に揮発し過剰作用のおそれがなく,水で簡単に洗い落とせるため,手荒れの心配が少ないのはアンモニア水である。
(2) 強いパーマ剤は得られないが,臭気が弱く作用も弱いため毛髪や皮膚に対しても悪影響をあたえず,手荒れの心配の少ないものは炭酸水素アンモニウムである
(3) 臭気がない反面,揮発しにくく皮膚への親和性が高いので,過作用のおそれがあり,水で洗い落としにくく手荒れに注意する必要があるのはモノエタノールアミンである。
パーマ剤第1剤に使用されるアルカリ剤に関する次の文章の( )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「アルカリ剤は毛を膨潤させる作用を持つが、pHが高いほど膨潤度は( A )なる。アンモニア水とモノエタノールアンは、ともに( B )である が、アンモニア水は( C )性が高く、モノエタノールアンは( C )性がない。このため、第1剤の作用時間中に、アンモニア水は( C )によりアルカリとしての作用が徐々に弱まるが、モノエタノールアミンは持続する。」
(1) A:小さく B:強アルカリ剤 C:凝集
(2) A:小さく B:弱アルカリ剤 C:揮発
(3) A:大きく B:強アルカリ剤 C:揮発
(4) A:大きく B:弱アルカリ剤 C:凝集
正解(3)
パーマ剤(パーマネント・ウェーブ用剤)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) パーマ剤に使用されているシステインは,酸化剤である。
(2) パーマ剤に使用されている臭素酸ナトリウムは,還元剤である。
(3) パーマ剤に使用されているモノエタノールアンは,アルカリ剤である。
(4) パーマ剤に使用されているチオグリコール酸は,界面活性剤である。
正解(3)
(1) パーマ剤に使用されているシステインは、還元剤である。
(2) パーマ剤に使用されている臭素酸ナトリウムは、酸化剤である。
(4) パーマ剤に使用されているチオグリコール酸は、還元剤である。