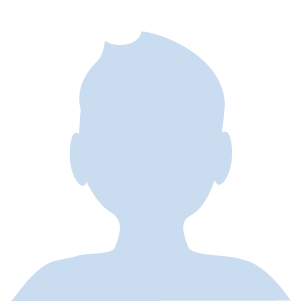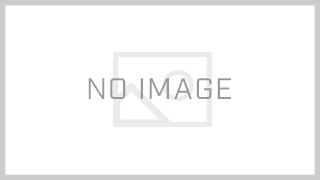飛鳥・奈良時代
男性の髪形
飛鳥・奈良時代の男性の髪形には、以下のような髪型があったとされています。
①角髪
飛鳥・奈良時代の髪形は、古墳時代同様、男性は角髪が多かったとされています。
②冠下の髷
朝廷の男性は、髻(もとどり)(髪を頭の上に集めて束ねたもの)の上に、袋状の冠物(かぶりもの)をかぶるスタイルの冠下の髻(かんかのけい)が多かったとされています。
女性の髪形
飛鳥・奈良時代の女性の髪形には、以下のような髪型があったとされています。
①肩のあたりで折り曲げて結ぶタイプ
前髪を束ねて、それを後ろに垂らし、肩のあたりで逆さに折り曲げて結んだ髪型。
②頭上一髷・頭上二髷
中央分けにした髪を途中から折り返して上げ、頭上で1つか2つの髷をつくる髪形。髷が1つなら、頭上一髷(ずじょういっけい)・2つなら頭上二髷(ずじょうにけい)と呼ばれます。
③四つ割
鬢を4つ作り、頭上で結んだ髪型。
朝廷の服装
三公服(礼服・朝服・制服)
飛鳥・奈良時代の朝廷では、中国にならった服制(身分や階級による服装のきまり)が導入されました。それによって、
- 式典の際に用いる正装(儀礼服)としての礼服(らいふく)
- 平常の宮廷勤めの際に着用する朝服、
- 下級官吏のための制服
の三公服の制度が定められました。
袍
飛鳥時代の武官の朝服では、幅の広いゆったりとした袖の袍(ほう)とよばれる上衣・下はズボン形式の袴を着用していたとされています。
庶民の服装
女性
女性の服装は、『天寿国繍帳』を見ると、上衣は、丸首で丈長のものを着用し、下半身は、裙/裳(も)の上に褶(ひらみ)を付けていました。
また、左肩から二重のたすきを斜めにかけています。
裙/裳(も)…スカート状の衣服
褶(ひらみ)…ヒダのあるスカート状の衣服
男性
男性は、丈長の上衣に、下衣は、袴(はかま)の上に褶を付たような服装だったことがわかります。
参考:天寿国繍帳
つまり、
- 女性は、スカートの上に、ヒダのあるスカート状の衣服を着ていた。
- 男性は、袴(ズボン)の上に、ヒダのあるスカート状の衣服を着ていた。
- 男女とも上着は、丈長
と言うことになります。
化粧
奈良時代の『鳥毛立女屏風』を観察すると、額に花模様を描く花鈿(かでん)、唇の両側に黒点や緑点を描く靨鈿(ようでん)の化粧の存在があったことわかります。
参考:鳥毛立女屏風
花鈿
紅で眉間にさまざまな紋様を描く、中国の特徴的な化粧。
靨鈿
唇の両側に黒点や緑点を描く、中国の特徴的な化粧。
三日月眉・柳眉・蛾眉
奈良時代末期の『万葉集』には、眉墨で眉を描く眉引きや、三日月眉(みかづきまゆ)や柳眉(りゅうび)などの言葉があり、眉を三日月や柳の葉などのように美しくたとえた歌が多あります。
三日月眉・・・三日月のような形の眉
柳眉・・・柳の葉のような形の眉
蛾眉(がび)・・・三日月だがやや太めの眉
平安時代
男性の髪形
冠下の髷&烏帽子
平安時代の男性の髪形は、奈良時代から引き続き冠下の髷でした。
かぶりものには、烏帽子(絹地に漆を塗った、やわらかく高く張った帽子)が略服の際に用いられるようになります。
朝廷の人だけでなく、庶民も自由に烏帽子をかぶり、常用するようになりました。
女性の髪形
平安時代の女性の髪型は、髪全体を長く垂らす垂髪(すいはつ)が多かったとされています。
垂髪
髪全体を長く垂らした髪型
鬢枇ぎ
貴族階級の女性は、垂髪の左右の鬢(びん)(頭の側面の髪)の一部を分け目から60㎝くらいのところで切りそぐ鬢枇ぎ(びんそぎ)という儀式を行い、成人女性のしるしとしていました。
当時の成人は、16歳でした。
なぜ垂髪が好まれた?
垂髪が好まれた理由には、以下のような理由があったとされています。
- 長い黒髪を尊ぶ文化が発達したから
- 人に顔を見せることが、はしたないこととされ、顔を隠すため(顔隠しという)
顔隠しの衣装(被衣・むしの垂衣)
顔を隠すための衣装には、以下のようなものがありました。
- 被衣(かづき)…身分ある女性が顔を隠すために頭から被った布
- むしの垂衣(たれぎぬ)…市女笠(いちめがさ)のまわりに布を垂らしたスタイル
市女笠とは?
デカ麦わら帽子のようなもの。スゲ(菅)などの材料で編まれた、中央に高く突起を作った笠のこと。
装身具が衰退?
古墳時代は、装身具によって身分や階層が区別されていましたが、奈良・平安時代になると、装身具は見られなくなります。
代わりに、服装により身分や階層が区別されるようになりました。
貴族の男性の服装
平安時代では、遣唐使が廃止されてから、髪形や服装、文化は国風化していき、貴族たちは贅沢を好み、衣服の種類も増え、デザインは華美になっていきました。
貴族たちは、朝廷に出仕する(勤めに行く)ときには、①束帯を着用し、日常着には、②直衣・狩衣を着用していました。
①束帯(宮廷勤め)
朝廷に出仕する(勤めに行く)ときに着用した一般的な朝服は束帯(そくたい)と呼ばれるものでした。
束帯は、中に着物のような服を着て、外側にボリュームのある大きな丸首の服を重ね、袴を着用します。
参考:束帯の画像
②直衣・狩衣(日常着)
貴族の日常着は直衣(のうし)と狩衣(かりぎぬ)でした。
- 直衣…指貫(さしぬき…裾を紐でくくれるようにした袴)をはき、外衣の色や文様を自由に選んだもの。
- 狩衣…元々は狩猟用の服装で、脇が開き、袖口がくくれるようになっているもの
参考:直衣の画像
参考:狩衣の画像
貴族の女性の服装
平安時代の貴族女性の公式の正装は唐衣裳(からぎぬも)でした。
唐衣裳とは?
一眼外側に唐衣を着て、その内側に表着、袿(うちぎ)、肌着の単を何枚も重ねた服装のことを言います。
やがて、唐衣を着て、その内側に表着、単、肌着の小袖を重ねるようになり、単重(ひとえがさね)と呼ばれるようになり、
平安時代末期には、唐衣裳の内着は5枚と定められ、五衣(いつつぎぬ)と呼ばれるようになり、
江戸時代には、十二単(じゅうにひとえ)と呼ばれるようになります。
【唐衣裳の名前の変化】
唐衣裳⇨単重⇨五衣⇨十二単
唐衣裳と単重の違い
| 外側 | ⇨ | ⇨ | 内側 | |
| 唐衣裳 | 唐衣 | 表着 | 袿 | 単 |
| 単重 | 唐衣 | 表着 | 単 | 小袖 |
平安時代の庶民の服装
平安時代末期ごろには、狩衣の一種である水干(すいかん)が下級官仕の制服、武士や庶民の日常着だったとされています。
平安時代の化粧
平安時代の化粧には、以下のような特徴がありました↓
眉毛を抜き、眉毛を描く
平安時代に入ると、眉毛を抜くようになり、成人のしるしとして、別の太めの眉を額に描くようになります。
お歯黒
歯を黒くする化粧であるお歯黒が行われるようになりました。
- 平安時代に、貴族階級の女性の成人のしるしとして行われるようになりました。
- 初期は、女性の間で行われていたが、次第に男性もお歯黒を行うようになりました。
平安時代は、貴族の成人のしるしと言って髪の毛を枇ぎ(鬢枇ぎ)、眉毛を抜き
何かと取っ払う時代!