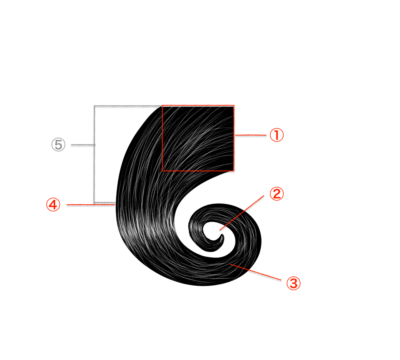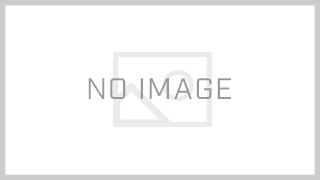日本髪
日本髪とは?
日本髪は、日本の風俗を代表するものの1つとして、古くから伝統的に受けつがれてきたヘアスタイルです。
日本髪の原型は、江戸時代(寛永年間)の兵庫髷と言われています。
日本髪は、徳川幕府による鎖国がによって、日本独自のものとして発達してきました。
徳川幕府の時代に現れた日本髪の種類だけでも女性で150種、男女子とも合わせて300種あるとされています。
日本髪の各部の名称
日本髪は、前髪、鬢、髱、髷から構成されています。

①前髪 ②鬢 ③鬢尻 ④前髷 ⑤後髷(いち) ⑥髷 ⑦根 ⑧髱
鬢(びん)について
日本髪は、両サイドの鬢(びん)が最も崩れやすいです。
崩れかかったときには、鬢出しでとかし、鬢窓(前髪と鬢との境のところ)を張り上げ、耳の後ろから鬢出しを入れて鬢の後ろをかき下ろします。
入浴や化粧のときには、鬢あげで上げておくと崩れ防止になります。
日本髪の種類
稚児髷
特徴
稚児髷は、江戸時代に発生した上流階級の髪型で、頭上、左右に分かれた高い輪をつくるものです。
どんな人の髪型?
明治時代に入ってから童女の髪型になりました。
現代では子どもの七五三などに用いられます。
桃割れ
特徴
桃割れは、左右に毛を分けて輪にし、後頭部で結び、髷をふくらませたものです。
どんな人の髪型?
明治時代入ってから少女が結うようになりました。
銀杏返し
特徴
銀杏返しは、江戸時代の末期から始まった髪型で、髷の上を2つに分け、左右に曲げて半円形に結んだ髪型です。
若い女性は髷を大きく結い、中年以上は小形に結う。
どんな人の髪型?
はじめは少女の髪型とされていましたが、しだいに年齢制限がなくなりました。
唐人髷
特徴
唐人髷は、丸い髷の前の部分が中央で割れていて、桃割れと銀杏返しを一緒にしたような形をしています。
江戸末期から行われるようになりました。
どんな人の髪型?
唐人髷は、少女の髪の結い方です
天神髷
天神髷は、銀杏返しの変形で、銀杏返しの髷の中央を髪で巻きでとめたものです。
島田髷
特徴
島田髷は、立体的な美と変化に富み、安定感のある髪型です。
日本髪の中でも最も代表的な髪型とされています。
種類
| 高島田、文金高島田 | 髷を高く結ったもの |
|---|---|
| つぶし島田 | 髷の中央を低く結ったもの |
| 結綿島田 | つぶし島田の中央を布で結び束ねたもの |
髷を高く結ったものを高島田、文金高島田とよび、髷の中央を低く結ったものをつぶし島田と呼びます。
結綿島田は、つぶし島田の中央を布で結び束ねたものです。
他にも、島田髷の種類はたくさんあります。
どんな人の髪型?
文金高島田は婚礼のときの髪型とされています。
高島田は、主に若い女性に結われるので、未婚者髷ともいわれます。
丸髷
特徴
丸髷は、江戸時代初期の勝山髷から起こったもので、頭頂部に楕円形の平たい髷をつけた髪型です。
若い人は大きな髷、年齢とともに小さい髷を使用します。
若い既婚者は赤、年長者は水色の手絡(てがら…日本髪に用いる布の髪飾り)をつけていました。
どんな人の髪型?
明治時代では、既婚者の証とされていました。
まとめ表
髪型と特徴
| 髪型名 | 特徴 | |
| 稚児髷 | 左右に分かれた高い輪をつくる | |
| 桃割れ | 左右に毛を分けて輪にし、後頭部で結び、髷をふくらませる | |
| 銀杏返し | 髷の上を2つに分け、左右に曲げて半円形に結う | |
| 唐人髷 | 桃割れと銀杏返しを一緒にしたような形 | |
| 天神髷 | 銀杏返しの変形で、銀杏返しの髷の中央を髪で巻きでとめたもの | |
| 島田髷 | 高島田、文金高島田 | 髷を高く結ったもの |
| つぶし島田 | 髷の中央を低く結ったもの | |
| 結綿島田 | つぶし島田の中央を布で結び束ねたもの | |
| 丸髷 | 頭頂部に楕円形の平たい髷をつけたもの | |
髪型と対応人物
| 髪型名 | 特徴 | |
| 稚児髷 | 童女の髪型。現代では子どもの七五三などに用いられる。 | |
| 桃割れ | 少女 | |
| 銀杏返し | はじめは少女の髪型とされていたが、しだいに年齢制限がなくなった。 | |
| 唐人髷 | 少女 | |
| 天神髷 | ー | |
| 島田髷 | 高島田、文金高島田 | 高島田は、若い女性に結われる(未婚者髷ともいわれる)
文金高島田は婚礼のときの髪型。 |
| つぶし島田 | ー | |
| 結綿島田 | ー | |
| 丸髷 | 既婚者 | |
日本髪と調和
日本髪には俗に、「粋な髪」 と「上品な髪」という言葉があります。
島田髷のなかでは、「つぶし島田」などは粋な髪といわれます。
粋な髪とは?
全体に線のくっきり出た髪が「粋な髪」とよばれます。
こんな髪が粋だ!
【粋な髪の特徴】
- 根の位置が下がり気味
- 髱が横に張らずに細め
- 髪全体に丸みが少ない
これは、すっきりした着こなしに合うように考えられています。
上品な髪とは?
「上品な髪」とは、全体にふっくらした感じの髪のことを言います。
こんな髪が上品だ!
【上品な髪の特徴】
- 髪の幅がやや広いもの
- 前髪に丸みをもったもの
- 体のやわらかみに調和しているもの
日本髪のバランス
日本髪は、顔の形に合わせてバランスを取ることが重要です。
以下の点に注意すると調和が取れて良いとされています。
前髪の張り出し(先端部分)
・・・鼻の頂点(鼻尖)の高さと揃えるとGOOD
鬢の下端
・・・鼻翼にそろえるとGOOD
髱の下端
・・・顎か、顎より少し上がった位置にそろえるとGOOD
日本髪の装飾品
日本髪の装飾品には、次のようなものがあります。
- 花簪(飾櫛)
- 花簪(前挿し)
- びら簪(前挿し)
- 平打ち(後挿し)
- 玉簪
- 芳丁
- 飾櫛(前櫛)
- 笄(中挿し)
- 根がけ
- 手絡(かけもの)
花嫁の文金高島田につける装飾品
花嫁の文金高島田につける装飾品には、次のようなものがあります。
- 中挿し
- 丈長(ひら元結)
- 羽根元結
- 後挿し
- 前挿し
- 前飾り
- 根飾り
- 飾櫛
日本髪の結髪道具
日本髪の結髪道具には、次のようなものがあります。
- 櫛(くし)
- 髢(かもじ)
それぞれ見ていきましょう!
①櫛(くし)類
日本髪の結髪用櫛(くし)類は、以下のようなものがあります
- 元結通し
- はまぐり歯
- きわ出し
- 鬢出し
- 鬼歯ねずみ歯
- 月形
- 毛筋の抜き歯
- 細歯のとかし櫛
- 中歯のとかし櫛
- 荒歯のとかし櫛
元結通し
元結通しは、桃割れや銀杏(いちょう)返しなどの輪ものを結うときに、元結を通して使う櫛(くし)
はまぐり歯
はまぐり歯は、全体の仕上げに使う櫛(くし)
きわ出し
きわ出しは、鬢(びん)の下の方の際、生え際の毛を整えるのに使う櫛(くし)
鬢出し
鬢出しは、鬢(びん)を裏からふくらませたり、形を整えたりする櫛(くし)
鬼歯ねずみ歯
鬼歯ねずみ歯は、仕上げに表面の毛の流れを整える櫛(くし)
月形
月形は、後髷(うしろまげ)の丸い部分をとかすのに使う櫛(くし)
毛筋の抜き歯
毛筋の抜き歯は、前髷(まえまげ)などを広げるのに使う櫛(くし)
細歯のとかし櫛
細歯のとかし櫛は、仕上げに使う最も目の細かい櫛。前髪・髱(たぼ)髪(びん)などを形づくるのに使う櫛(くし)
中歯のとかし櫛
中歯のとかし櫛は、荒歯と細歯の間に使う櫛(くし)
荒歯のとかし櫛
荒歯のとかし櫛は、おおまかに髪をとくのに使う櫛(くし)
②髢(かもじ)類
髢(かもじ)とは、髪の形を整えるために、つけ足す髪の毛のことを言います。
髢(かもじ)類は、以下のようなものがあります
- 根髢(ねかもじ)
- 紺紙(こんし)
- 前髪髢
- 前髪おさえ
- 前髪のすき毛
- 元結
- 鬢のすき毛
- 髷型(枕)髱のすき毛
それぞれ見ていきましょう!
❶根髢(ねかもじ)
根髢は、髷(まげ)にボリュームを出すために、根に結わえ付けて使用する髢(かもじ)
❷紺紙(こんし)
紺紙は、固練りの油を塗って、壊れにくくするために髱(たぼ)鬢(びん)髷 (まげ)の形に切って裏側に貼り付けて使用するもの
❸前髪髢
前髪髢は、前髪にボリュームを出すために、根に結わえ付けて使用するもの
❹前髪おさえ
前髪おさえは、結髪(けっぱつ)の際、前髪をおさえるもの。
❺前髪のすき毛
前髪のすき毛は、前髪の形を支えるために、内側に入れて使用するもの
❻元結
元結は、和紙をこより状にしたヒモ状のもの
❼鬢のすき毛
鬢のすき毛は、髪(びん)の形を支えるために、内側に入れて使用するもの
❽髷型(枕)
髷型(枕)は、髷(まげ)のボリュームを出しつつ軽量化を図るために使うもの
❾髱のすき毛
髱のすき毛は、髱(たぼ)の形を支えるために、内側に入れて使用するもの
かつら
かつらの使用上の注意
かつらの使用上の注意は、以下のようなものがあります
- 涼しく湿気の少ない所に保存し、ときどき風を通す。
- ほこりが付かないように箱におさめておく。